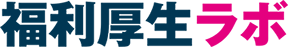従業員満足度の向上は、業績アップには欠かせないものです。
今回は、従業員満足度についてまとめました。

従業員満足度とは
従業員満足度とは、自社に対する従業員の満足度を表す指標。
英語では「Employee Satisfaction」と表現され、「ES」と略されます。
近年ではこの従業員満足度を向上させることこそが、企業の業績向上の鍵とされています。
ちなみに別の記事では、この従業員満足度をチェックする手法であるES調査について詳しく説明しています。
-

-
ES調査とは何か。企業がES調査をするべき理由
ES調査とは何か。また企業がES調査をするべき理由について、今回の記事で紹介します。 目次 ES調査とは何かES調査で何がわかるか基本情報キャリア形成、人材育成人間関係組織風土会社について業務について ...
続きを見る
では、一体どのようにすれば従業員満足度を向上させることができるのでしょうか?
次項から詳しく見ていきます。
企業ビジョンへの共感
簡単に言えば「何をしようとしている会社なのか」が明確にわかり、そこに共感でき「一緒に頑張りたい」と思えることが、従業員満足度を向上させる1つ目のポイントになるということです。
まずは会社が目指していることが、誰にとっても明確にわかるようになっていることが大切です。
そのためには、よくある経営理念のように難しい言葉の長文ではなく、従業員の誰もが理解できて忘れられないような一言で会社の存在意義・目的を表している必要があります。
例えば朝礼などでそれを暗唱させ、無理やり覚えさせるようなことは従業員満足度をむしろ下げてしまいます。
そして、その一言で表される会社の存在意義・目的は、魅力的なものでなくてはなりません。逆説的に言えばそれが「創業者の個人資産を増やす」であれば、それに共感し「一緒に頑張りたい」と思える人は基本的にはいないでしょう。
会社がやろうとしていること・目指していることそのものの社会的意義をきちんと見つめ直し、それを無駄な言葉を省いた短い言葉で表現することが大切です。
まとめると、企業ビジョンへの共感を生み出すためには、会社の存在意義・目的を魅力的な一言で表現し、それを従業員誰もが知っている状態を作ることが必要だということになります。
マネジメントへの納得感
「上司や会社が自分を見てくれていない」「自分は正当に評価されていない」と感じることは、従業員が離職する大きな理由のひとつです。
そうならないためには、「公正な評価制度」と「それを正しく運用できるマネジメント人材」の2つが必要です。
評価制度の一例には360度評価などがありますが、どんな評価制度も万能ではなくメリットとともにデメリットも必ずあります。自社の状態にあわせて最適な評価制度を構築していく必要がありますし、一度作ったら終わりではなく、常に従業員の声を聞きながらより良いものに更新していくことが大切です。
そのためにも、それを運用するマネジメント人材が、従業員の意見を吸い上げ、評価制度のブラッシュアップにフィードバックさせていく動きが求められます。
マネジメント人材の育成もきちんと教育プログラムを構築してスキル向上を図る必要がありますし、マネジメント人材自身の従業員満足度が低下していないかをウォッチし適宜調整をできる仕組み作りが必要になります。
自身の仕事が業績や社会に影響を与える実感
やはり、自分の仕事が会社の業績に良い影響を与えていて、社会に価値を提供できていると実感できれば、従業員満足度は高くなりやすいものです。
大切なのは、いかにそれを実感させることができるかです。
営業部門など、もともと自分の仕事の成果が数字で現れやすい部署の従業員は、比較的その実感を得やすいと思います。
ただし、そういった部門でも結果の数字だけではなく、行動量などのプロセスもできる限り数値化し、評価に組み込んでいったほうが、さらに自分の仕事の会社・社会への価値を実感してもらいやすくなるはずです。
さらに、管理部門・間接部門の従業員に対しては特に、その実感をもたせる工夫が必要になります。それがないと「営業ばかり評価されて自分はコストとしか思われていない」などと、よくある離職のパターンになってしまいます。
どの部門であっても仕事の成果をできる限り数値化し見える化し、いかに会社・社会に良い影響を与えているかを伝えていく場を設定することが大切です。
また、仕事の成果の数値化・見える化がきちんと実現できていれば、テレワークにおいても従業員を正しく評価・管理できる仕組み作りも実現しやすくなります。
職場の人間関係のストレスのなさ
厚生労働省が出している平成30年雇用動向調査結果の概況によると、特に若年層において「職場の人間関係」は離職理由の上位に入っています。
やはり多くの場合、仕事の時間は生活の中で大半を占めるものです。
そこでの人間関係のストレスは顧客満足度の低下に大きく影響します。
では、どのようにすれば良いでしょうか。
コミュニケーションを活性化させる目的で飲み会や社外イベントに力を入れるケースもよくあると思いますが、近年では若年層を中心に仕事とプライベートをきちんと分けたい人が増えているため、逆効果になる場合も多いため注意が必要です。
コミュニケーション活性化の場を設けるなら、給与が発生する通常の業務時間内で行うことが大切です。
できれば、人間関係のストレスがあった時には随時、上司や経営陣に気兼ねなく相談できる関係を構築できていることが理想です。
また、人間関係を悪化させる特定の人材がいる場合、それがたとえ業績の良い従業員であったとしても、再教育や場合によっては配置転換などの具体的な手を打っていくことが大切です。業績が良いからといって放置してしまうと、がん細胞が拡がるように組織全体に悪影響が拡がってしまいます。
職場環境の快適さ・労働条件への満足感
一言で「職場環境」と言っても様々な要素があります。
単純に勤務地・オフィスの環境もそのひとつですし、勤務時間の柔軟性やテレワークの推進度などの就業規則もそのひとつです。
やはり勤務するなら快適・便利な街にあるキレイなオフィスを望む人が多いと思いますし、柔軟な働き方を選ぶことができてワークライフバランスを実現できる就業規則を望む人が多いはずです。
また、労働条件もできるだけ高い給与や手厚い手当・待遇を望む人が多いはずです。
変えられる範囲でなるべくより良いものに変えていくべきですが、資本力や業態によって限界もあるはずです。
そこで重要になるのが、福利厚生の充実です。
世の中には様々な福利厚生サービスがありますが、低コストまたは無料で導入できるものも多く、従業員から見ても「うちの会社は色々工夫してくれている」と感じられ、従業員満足度の向上においてコストパフォーマンスの良い打ち手となることが多々あります。
まずは世の中にどのような福利厚生サービスがあるか調べ、自社の状況に合わせて導入しやすいものは積極的に導入していくことは、従業員満足度の向上にとって効果的な動き方になるかと思います。
福利厚生の基本については以下の記事を参考にしてください。
-

-
福利厚生とはなにか、なぜ重要なのか、種類、注意点について
福利厚生は、従業員満足度や定着率向上を考える上では絶対外せないポイントの一つ。 この記事では、福利厚生とはなにか、なぜ企業にとって重要なのか、種類、導入する上での注意点について説明します。 目次 福利 ...
続きを見る
-

-
【全13ジャンル】福利厚生サービスの種類についてご紹介します。
会社にとってなくてはならない福利厚生ですが、自社内で提供する福利厚生と、外部に委託(アウトソーシング)する福利厚生、各種サービスを導入する福利厚生などに分かれています。 世の中にはたくさんの福利厚生サ ...
続きを見る
最後に
今回の記事では、従業員満足度を向上させる5つのポイントをご紹介しました。
この5つの実践を通して従業員満足度を向上させることで、離職率が低下したりより優秀な人材を採用しやすくなったり、従業員のモチベーションが上がって生産性も向上し、顧客満足度の向上にも繋がったりします。
今後も続くことが予測される少子高齢社会の中で、労働人口もまた継続的な減少が予測されます。企業間における従業員満足度の差は、今まで以上に大きな競争力の差となっていくはずです。
従業員満足度を向上させ、より良い会社になるために今回の記事を参考にして頂ければ幸いです。